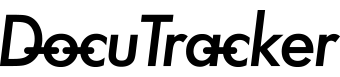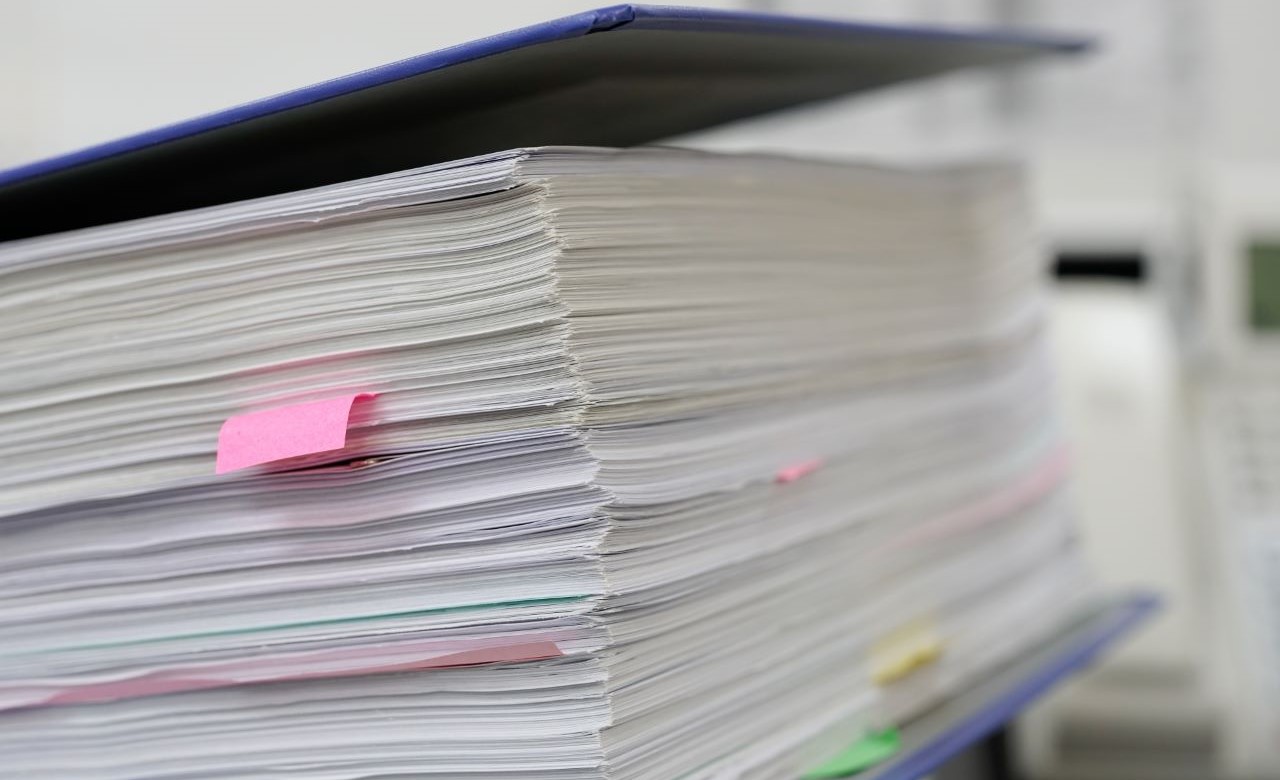ナレッジ
ナレッジ データ保存関連
電子帳簿保存法で紙保存と併用する際の重要ポイントを解説
電子帳簿保存法とは、従来は紙での保存が義務付けられていた帳簿や書類に対して、電子データの保存を可能とする法律です。電子取引に関しては対応の義務がありますが、取引先とのやり取りのなかで、紙の請求書やレシートを受け取る場合もあるでしょう。一部の書類については、改正電子帳簿保存法においても紙のまま保存することが認められています。今回の記事では、保存できる紙の書類や、紙での保存と電子データを併用する際のポイントをご紹介します。
改正により2024年1月から電子取引データの紙での保存は原則不可に
電子帳簿保存法の正式名称は、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」です。(以下、電子帳簿保存法と記載)電子帳簿保存法の改正により、2024年(令和6年)1月1日からは電子取引における電子データ保存が完全義務化されました。電子取引により作成、受領した書類は原則紙での保存ができません。
データ保存方法の区分
電子帳簿保存法では、データの種類によって保存方法の区分を定めています。詳しくは、以下の通りです。
電子帳簿等保存
会計ソフトやExcelなどで作成する国税関連帳簿や書類の保存方法です。下記の書類が該当します。・仕訳帳、総勘定元帳、売上帳などの国税関係帳簿
・損益計算書や貸借対照表などの決算書類
・PCで作成した見積書や請求書、納品書、領収書などを紙で取引相手に渡したときの控え
など
スキャナ保存
紙の書類をスキャナで電子データにして保存する方法です。下記の書類が該当します。
・取引相手から紙で受け取った契約書や見積書、注文書、納品書などのスキャンデータ
・取引相手に紙で渡す契約書や見積書、注文書、納品書などのスキャンデータ
電子取引データ保存
電子データで注文書や契約書、見積書などをやり取りした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。電子取引は、下記が該当します。
・Web請求書
・クラウド取引
・EDI取引
・メール
紙での保存が可能な書類
電子取引においてはデータの保存が必須で、原則紙での保存はできません。電子取引ではなく紙で取引を行っている場合にはデータ保存は必須ではなく、紙での保存が可能です。
紙で作成・受領した書類
請求書、契約書、領収書などの取引関係の書類は紙での保存が可能で、電子データの保存と併用できます。自社で発行した紙の領収書の控えや、取引先から郵送で届いた請求書といったものが該当します。
なお、これらの書類は、「スキャナ保存」することも可能です。スキャナ保存をする場合は、紙の書類は廃棄してもかまいません。PDF形式のデータで受領した場合は、プリントアウト自体は禁止されていませんが、電子取引となるためPDFデータの保存が必要です。
自社のみが使う国税関係帳簿・国税関係書類
「電子取引」を行わない自社向けの書類は、紙での保存が可能です。例としては、会計ソフトウェアを使って仕訳帳や総勘定元帳、現金出納帳などの国税関係帳簿をPCで作成した場合などが該当します。
電子取引における紙での保存が廃止された理由
では、なぜ電子取引において、紙での保存が禁止されたのでしょうか。主な理由としては、経理業務の電子化促進と、データの信頼性確保が挙げられます。
経理業務の電子化促進
もともと電子帳簿保存法は、経理業務の電子化を進めるための法律です。紙で帳簿や書類を保存すると、内容の確認や集計などの作業や管理が煩雑になります。電子帳簿保存法に従ってデータを電子の形で保存する仕組みを整えると、領収書をスマホで読み取って経理担当に送付する、といったスムーズな業務が可能になります。それまで社内でしかできなかった経理処理も、テレワークや出張先などから迅速に行えるようになるでしょう。
また、電子データなら書類の保存場所や、書類のファイリングも不要になります。国税関係帳簿、国税関係書類は5~10年の保存が必要であることから年々管理コストがかさみますが、紙の書類の保管が不要となれば管理コストを削減できます。
データの信頼性確保
電子データをプリントアウトした場合、紙の書類と電子データが同一であることを証明できないという問題もあります。同一である証明ができないために、内容が改ざんされる可能性があるのです。また、紙は劣化によって内容が読めなくなるリスクもあります。電子データなら、比較的簡単に「改ざんされていないこと」を証明できます。
電子帳簿等保存における保存要件
帳簿等を電子データで保存するにあたっては、遵守すべき要件があります。電子帳簿保存法で定められている区分のうち、電子帳簿等保存における「優良な電子帳簿」の要件は下記の通りです。
・内容の訂正・削除や業務期間後の入力を行ったことがわかるシステムを利用する
・帳簿と、他の関係する書類について相互で関連性を確認できる
・システムや周辺機器の説明書や仕様書などの関係書類を備え付ける
・取引年月日、取引金額、取引先により検索できる
・日付または金額の範囲指定、その他2つ以上の条件により検索できるか、税務職員による電子データのダウンロードの求めに応じられる
なお上記を満たし、かつ届け出を提出している場合には、過少申告加算税の軽減措置の適用を受けられます。
スキャナ保存・電子取引における保存要件
スキャナ保存と電子取引におけるデータ保存は、保存要件として「真実性の確保」「可視性の確保」の2つが定められています。
「真実性の確保」と「可視性の確保」
「真実性の確保」とは、データに偽造や虚偽がないと証明することです。具体的にはタイムスタンプを付与することや、データ訂正ができない仕組みになっていること、組織内で訂正・削除のルールを定めていることが挙げられます。
「可視性の確保」とは、保存したデータをいつでも閲覧できるようにすることです。情報システムやプリンターに説明書等を備え付けること、日付・金額・取引先ほかの条件で検索できるように検索機能を確保することなどが求められます。
スキャナ保存の保存要件
スキャナ保存では、下記の保存要件に従う必要があります。
・早期入力方式か業務処理サイクル方式で入力する
・スキャンしたデータにタイムスタンプを付与する
・重要書類(契約書や領収書、請求書、領収書など)に対して、関連帳簿との相互関連性を確認できるようにする
・14インチ以上のカラーディスプレイ、カラープリンターを備え付ける
・整然とした形式、4ポイント以上の文字の大きさ、書類と同等の明瞭さで、拡大/縮小ができ、速やかに出力できる
・システムや周辺機器の説明書や仕様書などの関係書類を備え付ける
・解像度200dpi以上、24ビットカラーで読み取る
・取引年月日、取引金額、取引先により検索できる
・日付又は金額の範囲指定、その他2つ以上の条件により検索できるか、税務職員による電子データのダウンロードの求めに応じられる
電子取引のデータ 保存要件
電子取引のデータは、下記の保存要件を満たす必要があります。
・下記1~4のいずれかの対処を行う
1.タイムスタンプが付与された後に取引情報の授受を行う
2.取引情報の授受後速やかにタイムスタンプを付与し、保存者または監督者の情報を確認できるようにする
3. 記録事項の訂正・削除を行った場合に確認できるシステム、または訂正・削除ができないシステムを使う
4. 正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理のルールを定めて運用する。
・システムや周辺機器の説明書や仕様書などの関係書類を備え付ける
・取引年月日、取引金額、取引先により検索できる
・日付又は金額の範囲指定、その他2つ以上の条件により検索できるか、税務職員による電子データのダウンロードの求めに応じられる
電子帳簿保存法に対応するには専用のシステム導入もおすすめ
保存要件に挙げられている「タイムスタンプ」とは、ファイルが改ざんされていないことを証明できる技術のことを指します。タイムスタンプを付与できるサービスを導入すれば、電子帳簿保存法で求められている「データが改ざんされていないことの証明」ができるため、電子帳簿保存法への対応方法としてもおすすめです。
DocuTrackerはクラウドストレージにアップロードしたファイルに対し、自動でタイムスタンプを付与してくれるサービスです。クラウドストレージに対象データを保存する場合、DocuTrackerであれば、ブロックチェーン技術(※)を用いて、「改ざんされていないこと」を証明することができます。高度なブロックチェーンの技術を活用してタイムスタンプの生成を行っており、データを改ざんしようとすると前後のデータの不整合が起こるため、改ざんは極めて困難です。
※ブロックチェーン……暗号技術を用いて分散的に処理・記録する技術。DocuTrackerはプライベートブロックチェーン「mijin」を利用しています。
DocuTrackerを利用できるクラウドストレージサービスは、Google ドライブやMicrosoft OneDrive、Dropbox、Box。これらのサービスをすでに利用している場合は、簡単に導入できます。
電子書類・データが改ざんされていないことを証明し、保管履歴の証明が可能。法人の場合には特におすすめ。DocuTracker、詳しくはこちら ≫
まとめ
改正された電子帳簿保存法により、2024年1月1日からは電子取引における電子データの保存が義務付けられ、電子取引に関しては紙での保存が原則認められなくなりました。ただ、紙で作成・受領した書類や自社のみで使う国税関係書類などは紙での保存が認められているため、紙保存と併用する運用も可能です。電子帳簿保存法への対応としては、タイムスタンプを付与できるサービスの導入も一つの手段です。この機会に、検討してみてはいかがでしょうか。